すべて


2-6|利休の罪因 ~木像の安置~|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
大徳寺三門に自身の木像を安置した利休。その行為は宗教的禁忌を犯すものとされ、豊臣秀吉の怒りを買う直接のきっかけとなりました。木像は磔にされ、罪状は高札に滑稽に掲げられた——。だが、その背後には利休の影響力を恐れた政治的な意図も見え隠れします。


2-7|利休の罪因 ~売僧の嫌疑~|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
千利休が切腹を命じられた理由には、茶器売買に関する不正もありました。自らの企画による道具を高額で売買し、強大な経済力を持ったことが秀吉の怒りを買ったのです。その背景には、茶の湯の理念の相違や政権内の勢力争いも関係していたと考えられています。


2-8|利休の死後|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
利休の死後、千家は一時断絶状態となりますが、門人たちが茶の湯を守り続け、やがて千少庵や宗旦を経て三千家が成立します。高桐院に残る聚楽屋敷の遺構や、数寄道具の継承にその痕跡が見られ、利休の精神は今も茶の湯の中に息づいています。


2-9|利休の史料|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
千利休を深く知るための手がかりはどこにあるのか?本記事では『山上宗二記』をはじめとする主要文献に加え、利休自身の書状や千家伝来の文献、署名の変遷や代筆説などを詳しく紹介。茶の湯の精神がどのように記録され、伝承されてきたのかを史料に基づき明らかにします。
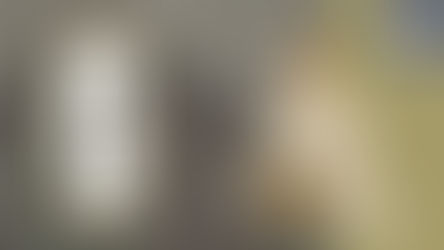

3-1|遺偈とは|第3回 利休の遺偈|千宗易利休|抛筌斎
辞世の句として知られる「利休の遺偈」——それは単なる詩ではありません。禅僧が悟りの境地を表すために遺す詩文「遺偈」は、千利休にとっても人生の総決算であり、茶の湯の精神を象徴する最期の言葉でもあります。本記事では、その宗教的背景と詩文としての意味を深く解説します。


3-2|利休の遺偈|第3回 利休の遺偈|千宗易利休|抛筌斎
千利休が死の直前に遺した偈は、単なる辞世の句ではなく、禅と茶道を極めた者の悟りの詩文です。「人生七十 力囲希咄」に始まるこの言葉は、仏の教えすら断ち切る覚悟と、無我の境地への昇華を表しています。命をかけて表現されたその精神を、語句ごとに解釈しご紹介します。


4-1|利休の茶の湯|第4回 利休の茶の湯|千宗易利休|抛筌斎
千利休が大成させた「わび茶」とは何か。豪華な書院茶湯から脱却し、狭く簡素な草庵茶室、見立道具、精神性を重んじた一期一会の思想など、日本文化に根づく茶の湯の美と心を形作った利休の革新をご紹介します。


5-1|利休四規とは|第5回 利休四規|千宗易利休|抛筌斎
「利休四規」とは、茶の湯の大成者・千利休が遺した精神的指針。「和・敬・清・寂」の四語に、茶道の本質と人の生き方が凝縮されています。本記事では、その全体像と精神背景に迫り、次章から各理念を詳しく探ります。


5-2|和敬清寂|第5回 利休四規|千宗易利休|抛筌斎
千利休が説いた「利休四規」は、茶の湯の精神を示す「和・敬・清・寂」から成り立ちます。それぞれの語は作法を超えた哲学的な理念として、現代においても深い意味を持ち続けています。本記事では各語の意味と実践を丁寧に解説し、「わび茶」の根幹に息づく精神に迫ります。


6-1|利休七則とは|第6回 利休七則|千宗易利休|抛筌斎
「利休七則」とは、『千家開祖/抛筌斎千宗易(利休)』が茶道の心得として説いた七つの教え。夏は涼しく、冬は暖かく、炭は湯が湧くように、茶は服のよきように――誰もが知るような言葉こそ、最も深く、最も難しい。利休が弟子に語った逸話を通じて、その実践の難しさと深みを読み解きます。


6-2|利休七則|第6回 利休七則|千宗易利休|抛筌斎
千利休が説いた「利休七則」は、茶の湯の心得を簡潔に表した七つの教え。「服のよきように」「炭は湯の沸くように」など、誰でも理解できる言葉の中に、深い精神と日常への応用が込められています。日々の暮らしを見つめ直すきっかけとなる、その内容を一項ずつ丁寧に紐解きます。

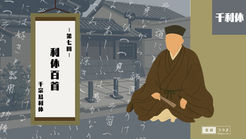
7-1|利休百首とは|第7回 利休百首|千宗易利休|抛筌斎
「利休百首」は、千利休の茶道の精神を三十一文字で詠んだ百首の和歌。玄々斎が整理し、咄々斎の法護普須磨 (反古襖)に記されたこの歌集は、茶道の奥義を伝える重要な指針とされています。茶の湯の修練者にとって、その一首一首が日々の稽古を照らす道標となるでしょう。


7-2|一首 ~ 十九首|第7回 利休百首|千宗易利休
1首から19首では、茶の湯を学ぶ上での基本的な心構えや稽古の姿勢、道具との向き合い方が詠まれています。茶の湯の修練において大切な“初学の精神”を、利休は一首一首に込めました。
各首には、それぞれの意味や背景を丁寧に解説していますので、日々の稽古の指針としてお役立てください。


7-3|二十首 ~ 三十九首|第7回 利休百首|千宗易利休|抛筌斎
20首から39首では、茶室の設えや点前における動作、道具の扱いなど、日々の稽古に欠かせない所作の心得が詠まれています。見落としがちな細部にこそ茶人の姿勢が表れます。
各首の和歌に込められた教えを、現代の視点から読み解いた解説を添えてご紹介します。


7-4|四十首 ~ 五十九首|第7回 利休百首|千宗易利休|抛筌斎
40首から59首では、四季に応じた茶会の設えや、亭主としての心配り、そして「わび」の美意識が語られています。自然と人とが調和する空間に利休の感性が宿り、一首一首にその静かな眼差しが映し出されています。
すべての首に対し、現代の稽古やもてなしに通じる解説を付しています。


7-5|六十首 ~ 七十九首|第7回 利休百首|千宗易利休|抛筌斎
60首から79首では、師弟関係の在り方や技術と精神の修練、設えの美意識といった茶人の覚悟が詠まれています。道具の取り合わせに込められた心配りから、日々の稽古を支える審美眼の重要性が浮かび上がります。
各首に沿った解説を通じて、利休の教えが現代にどう生きるかを紐解いていきます。


7-6|八十首 ~ 百二首|第7回 利休百首|千宗易利休|抛筌斎
80首から102首には、利休が晩年に至って到達した哲学的な境地が表現されています。生と死、自然との一体感、そして静寂のなかに見出される美。茶の湯を超えて人生そのものに通じる言葉が、深く穏やかに語りかけてきます。
それぞれの首について、思想的背景をふまえた解説を添えてご紹介しています。


7-7|利休百首全首一覧|第7回 利休百首|千宗易利休|抛筌斎
『利休百首』全102首を一覧形式で掲載したページです。茶の湯における基本の心得から精神の深奥に至るまで、千利休の教えが三十一文字に凝縮されています。各首の意味や背景を丁寧に解説した5回構成の記事と併せてご活用ください。全首一覧と解説を収めた資料PDFは無料でダウンロードいただけます。



