すべて


10-1|茶道の転換 ~教養としての茶道~|第10回 近代茶道の幕開け|大正時代~現代|茶道の歴史
昭和十五年、利休三百五十年遠忌に多くの女性門弟が参列したことは、茶道が教育として根付いた証でした。
明治以降、良妻賢母教育の一環として女学校で茶道が教えられ、戦後もその流れは続きます。
今回は、茶道が数寄から“学び”の場へと変化した近代の姿をひもときます。


10-2|献茶 ~献茶が大衆を魅了~|第10回 近代茶道の幕開け|大正時代~現代|茶道の歴史
明治から昭和にかけて、茶道は神仏への祈りから文化行事へと変化しました。
「献茶式」や「大茶会」は格式を保ちながらも大衆を巻き込み、やがて全国で行われる行事へと発展。
今回は、茶道が万人に開かれる契機となった献茶の歴史をたどります。


10-3|茶の湯と生きる ~あとがき~|第10回 近代茶道の幕開け|大正時代~現代|茶道の歴史
全10回にわたる「茶道の歴史」の締めくくり。
道具や作法にとどまらず、茶道に宿る精神や生き方に光をあてながら、現代と未来に向けた茶道の役割を考察します。
今こそ見直したい、“静寂”という心の価値とは。


茶道年表|前期|神話の茶から利休の自害まで|利休没以前|茶道の歴史|資料(PDF)無料ダウンロード
「茶道は、いつ、どこから始まったのか?」——この問いに迫る鍵は、利休より前の時代にあります。仏教儀礼としての茶、村田珠光・武野紹鷗の思想、そして「わび茶」の誕生へと至る流れを、年表でたどってみませんか?


茶道年表|後期|三千家の成立から今日まで|利休没以後|茶道の歴史|資料(PDF)無料ダウンロード
千利休の死は、終わりではなく始まりだった——。三千家の成立、武家の儀礼化、近代の茶道教育など、利休亡きあとの茶道がどう継承・変容していったのかを、年表でひもときます。
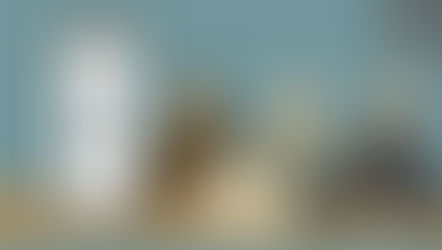

0-1|千家とは|千利休の道系を辿る|千家|茶道辞典
茶道辞典 ■ 千家 ■ 千家とは ❚ 千家とは 千家~せんけ~とは、千家開祖/抛筌斎千宗易利休(1522-1591)を祖とし息子の千家二代/千少庵宗淳(1546-1614)、孫の千家三代/咄々斎元伯宗旦(1578-1658)の三代を通じて確立された茶家のことを指します。 千家開祖/抛筌斎千宗易(利休)の提唱した茶道の思想や美意識、茶室・作法のあり方を受け継ぎ、後世に伝える家系として知られています。 注釈 広義においてはこの三代に加え、後の三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)も含めて「千家」と称されることがありますが、茶道プラスでは前述の三代を「千家」とし、その後に分かれた三家を「三千家」として区別しています。 千家開祖/抛筌斎千宗易利休の没後は長男の堺千家/千道安紹安(1546-1607)が、本家である堺千家の家督を継承するが後嗣ぎがなく一代にて断絶。 次男の千家二代/千少庵宗淳が京都の千家(京千家)を再興し、さらに孫の千家三代/咄々斎元伯宗旦が後を継ぎ、のちの三千家(表千家・裏千家・武者小路千家)の礎を築きました。 こうして、千家開祖/抛筌斎


0-2|千家開祖|抛筌斎|千宗易利休|1522-1591|千家|人物名鑑
人物名鑑 ■ 千家 ■ 抛筌斎|千宗易利休|1522-1591 ❚ 千利休とは? 千家開祖/千宗易利休(1522-1591)は、今日の茶道の基礎を築いた最も著名で茶道の歴史を語る上で最重要の茶人です。 千利休はそれまでの貴族や武家などの絢爛豪華な「茶」を、簡素で自然な美を尊び、静けさや調和を重んじる「侘び茶」として完成させました。 書院や会所で行われていた喫茶を、茶室という小さな空間へ移し、点前を行う道具の選定から制作、また「茶を点てる」、「懐石を食す」、その所作のひとつひとつに意味を持たせました。 こうして千利休は茶を通じて精神を整える「道」として茶道を大成させたことで知られています。 ❚ 千利休のあゆみ 千家開祖/千宗易利休は大坂・堺の商人の家に生まれ、若い頃から茶の湯に親しみ、当時の名茶人である武野紹鴎(1502-1555)に師事して茶道の技法や精神を学びました。 室町末期から安土桃山時代にかけて、茶の湯は武士や豪商の間で広まり、精神修養や社交の場として重要視されました。 千家開祖/千宗易利休はその中で、茶室の空間や道具の設えに独自の美学


0-3|千家二代|少庵宗淳|1546-1614|千家|人物名鑑
人物名鑑 ■ 千家 ■ 二代|少庵宗淳|1546-1614 ❚ 花押|署名 ❚ 出自 [父]宮王三郎三入(生没享年不詳)と[母]千宗恩(生年不詳-1600)との間に生まれる。 その後、[母]千宗恩が[養父]千家開祖/抛筌斎千宗易利休と再婚したことにより、千家の養子となり、以後は千家の一員として育てられる。 しかし千家二代/千少庵宗淳(1546-1614)は幼少の頃より先天的な病により片足に障害を抱えており、また、同年代でありながら千家本家の[義兄]千道安紹安(1546-1607)がいたことなども影響し、千家内での立場が弱かった事実が後世の歴史史料より確認されている。 その後、[養父]千家開祖/抛筌斎千宗易利休の娘である[妻]亀(喜室宗桂信女)(生年不詳-1587)を娶り、天正六年(1578年)には長男である修理(のちの千家三代/咄々斎元伯宗旦(1578-1658))が生まれる。 生 没 享 年 生年:天文十五年(1546年) 没年:慶長十九年(1614年) 九月七日 享年:六十九歳 出 生 父:宮王三郎三入 母: 千宗恩 養父:千家開祖


0-4|千家三代|咄々斎|元伯宗旦|1578-1658|千家|人物名鑑
人物名鑑 ■ 千家 ■ 三代|咄々斎|元伯宗旦|1578-1658 ❚ 花押|署名 ❚ 出自 [父]千家二代/千少庵宗淳(1546-1614)の長男としてうまれる。 母は[祖父]千家開祖/抛筌斎千宗易利休(1522-1591)の六女・亀(生没享年不詳)。 ※一説には叔父にあたる千道安紹安(1546-1607)の子ではないかという異説も伝えられている。 その出自には諸説あるものの、[祖父]千家開祖/抛筌斎千宗易利休の流れを汲む千家の後継者として、茶の湯の発展に大きく寄与することとなる。 生 没 享 年 生年:天正六年(1578年) 没年:万治元年(1658年) 十二月十九日 享年:八十一歳 出 生 父:千家二代/千少庵宗淳 母:[祖父]千家開祖/抛筌斎千宗易利休の六女・亀 名 幼名:修理 名:宗旦 一字名: 旦 通称:詫び宗旦 / 乞食宗旦 号: 咄々斎 / 咄斎 / 元叔 / 宗旦 / 寒雲 / 隠翁 / 元伯 兄 弟 弟(次男):山科宗甫(生年不詳-1666) 室 先妻:不明(生没年不詳) 後妻:宗見(生没年不詳) 子 先妻 長男:


1-1|利休の祖|第1回 利休の出自|千宗易利休|抛筌斎
千利休の祖先は、果たして本当に将軍家に仕えた名家だったのか——?
祖父・田中千阿弥とされる人物には複数の伝承が残る一方で、その多くは裏付けを欠き、矛盾も含まれています。
姓の由来、同朋衆との関係、記録上の空白——今なお多くの謎に包まれた利休の出自を、現存する史料をもとに読み解いていきます。


1-2|利休の出自|第1回 利休の出自|千宗易利休|抛筌斎
利休の「家族」は、なぜこれほど多くの人物と縁を持ったのか?
先妻・後妻それぞれとの間に多数の子をもうけ、商家や僧侶、茶人と広く婚姻関係を築いた利休。さらに、連れ子である少庵を養子に迎えた背景には、家の継承と思想の伝承という戦略が見え隠れします。
千家の礎を築いた“家族構成”を紐解きます。


1-3|利休の師|第1回 利休の出自|千宗易利休|抛筌斎
利休に師はいたのか? もしそうなら、誰が彼の「茶」と「こころ」を育てたのか?
堺の豪商・武野紹鷗から「侘び」を学び、大徳寺の禅僧たちから精神的な軸を得た利休。複数の師の存在が、利休の思想を深め、多層的な茶の湯を形づくっていきます。
その師弟関係の中に、利休という存在の核が見えてきます。


1-4|利休の門下|第1回 利休の出自|千宗易利休|抛筌斎
利休の門弟は、天下人から町衆まで幅広かった——。
武野紹鷗に学び、大徳寺で禅を修めた利休は、自らの「茶と精神」を豊臣秀吉や蒲生氏郷、古田織部など、あらゆる層に伝え広めていきました。
利休という“個人”から始まった茶の湯の哲学が、いかにして“流派”や“文化”として広がったのか。その源流をたどります。


2-1|利休の生い立ち|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
利休は武将ではなく、商人の家に生まれた――。
その出発点は、堺の町衆文化に根ざした「茶のある日常」。
北向道陳・武野紹鷗という二人の師のもとで茶の湯に触れ、大徳寺の禅僧と出会い、精神を深めていく。
一人の町人が、いかにして“茶聖”へと至る道を歩み始めたのか。堺という都市の力とともに、その原点を探ります。


2-2|信長と利休|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
天下人・信長は、なぜ茶人を重用したのか?
その背景には、権威の象徴としての“茶の湯”がありました。
今井宗久・津田宗及とともに「天下三宗匠」と呼ばれた利休は、文化を担う存在として政権に迎えられます。
茶と政治が交差する時代、宗易は何を学び、何を築いたのか——不審庵の誕生とともに、その足跡をたどります。


2-3|秀吉と利休|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
なぜ一介の茶人が、天下人の右腕となり得たのか?
信長亡き後、秀吉に仕えた利休は、聚楽第に居を構え、禁中茶会に参仕、ついには「利休居士」の号まで賜ることに。
政治の場にも踏み込むその姿は、もはや茶人の域を超えていました。
秀吉と利休の関係が、日本文化と権力の結びつきを象徴する瞬間を迎えます。


2-4|秀吉との対立|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
なぜ利休は処刑されなければならなかったのか?
秀吉の権威を支えた茶匠は、いつしかその象徴としての存在感が逆に重荷となり、最期には首を晒されるまでに。
北野大茶湯の成功の裏で進行していた亀裂、そして利休が選んだ「切腹」という最期にこめられた美学と覚悟を読み解きます。


2-5|居士号|第2回 利休の生涯|千宗易利休|抛筌斎
「利休」という名は、いつ、どのように授けられたのか?
正親町天皇からの勅諡とされる一方で、利休自身の師・大林宗套が生前に授けたという説も。
肖像画や書状の記録に見られる不整合を追いながら、「利休」号をめぐる真実に迫ります。



