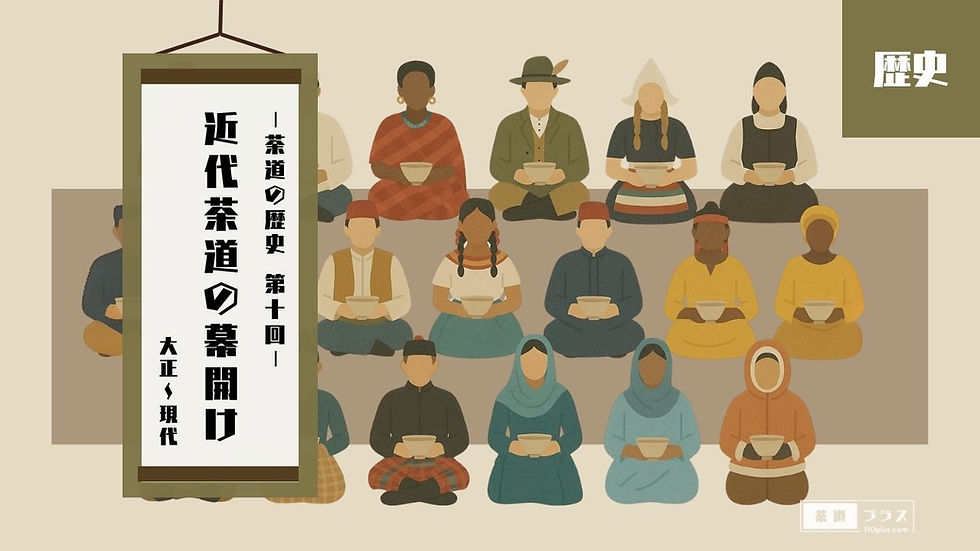10-2|献茶 ~献茶が大衆を魅了~|第10回 近代茶道の幕開け|大正時代~現代|茶道の歴史
- ewatanabe1952

- 2025年4月12日
- 読了時間: 5分
全10回 茶道の歴史

■ 第10回 近代茶道の幕開け [2/3] ■
大正時代 ~ 現代
❚ 祈りから、万人の文化へ
茶の湯は、どのようにして“万人のもの”へと広がっていったのでしょうか。
神仏への祈りから始まった「献茶」が、やがて人々を惹きつける文化行事へと発展していきます。
格式を保ちつつも開かれたその茶の場は、茶道が広く親しまれる契機となりました。
今回は、明治以降の献茶式と大規模茶会の歩みをたどります。
❚ 北野天満宮から始まる献茶の伝統

明治十三年(1880年)、京都『北野天満宮*』で初めての正式な「献茶式*」が執り行われました。
この行事を皮切りに、神仏にお茶を献じる「献茶」は全国に広がり、やがて大衆を巻き込む大規模な文化行事として定着していきます。
中でも注目されるのが、明治三十一年(1898年)に行われた『豊太閤三百年忌祭』です。
京都・東山の「豊国廟」における献茶式を中心に、京都市内の四十カ所あまりの寺社を会場として、二十日以上にわたり茶会が開催されました。
❚ 一万人を魅了した「昭和北野大茶湯」

その後も大規模な催しは続き、昭和十一年(1936年)には、『北野大茶湯*』から数えて三百五十年の節目を記念し、『昭和北野大茶湯*』が開催されました。
これにあわせ、十月八日から五日間にわたり、北野天満宮をはじめ、京都・鷹峯の『光悦寺*』、紫野の『大徳寺*』など、市内三十カ所以上で連日茶会が開かれ、参加者は一万人を超えました。
またこの際の茶席では、益田鈍翁、『根津青山*』など著名な数寄者や茶道具商、家元社中らが席主(亭主)を務めるという豪華な顔ぶれでした。
❚ ラジオ中継と全国への広がり
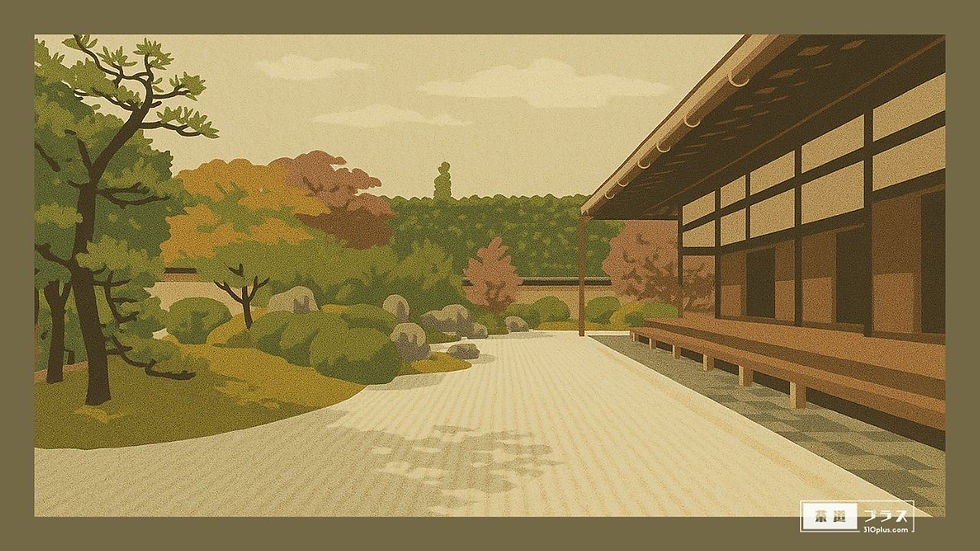
さらに、昭和十五年(1940年)四月二十一日から四日間にわたり『利休居士三百五十年遠忌*』が大々的に開催されました。
四月二十一日の献茶式はラジオ中継され全国へと発信され、翌日からの三日間は『大徳寺』山内七カ所の茶席にて茶会が行われ、延べ五千人以上の参列者を迎えたと伝えられます。
また同時開催された講演会には、学生やサラリーマンなどの一般市民が多数詰めかけ、満員御礼の盛況ぶりでした。
❚ 大衆化した茶道文化の原点
このように、明治から昭和にかけての「献茶」や「大茶会」は、茶の湯が特権階級だけのものではなくなり、万人に開かれた文化として根づいていった歴史的な契機であったといえます。
神仏への祈りから始まった「献茶」は、やがて民衆と茶の湯をつなぐ橋となりました。
ラジオ中継や全国的な参加を通じて、茶道は格式を保ちながらも“人々のもの”として広がっていきました。
次回は、戦後における茶道の国際化と現代に至る展開を見ていきましょう。
登場人物
益田鈍翁
……… 三井財閥|実業家|数寄者|孝|1848年―1938年
根津青山
……… 実業家|嘉一郎|1860年―1940年
用語解説
0
――
0
――
0
――
0
――
根津青山
―ねづ・せいざん―
1860年―1940年。明治から昭和にかけて活躍した実業家・茶人・文化人で、鉄道事業をはじめ多くの産業振興に貢献しました。茶道や書画、古美術に深い造詣を持ち、自邸に設けた「根津美術館」(東京・南青山)は、東洋美術の名品を収蔵・公開する場として今も高い評価を受けています。数寄者としても知られ、茶の湯を通じて日本文化の保存と普及に尽力しました。近代の財界人文化人の代表的人物です。
光悦寺
―こうえつじ―
京都市北区鷹峯にある日蓮宗の寺院で、江戸初期の芸術家・本阿弥光悦が徳川家康から土地を拝領し、芸術村「光悦村」を築いた地に創建されました。光悦の没後、彼を偲んで建てられた寺であり、茶室「大虚庵」など数寄屋建築が点在します。自然と調和した庭園や紅葉の名所としても知られ、書・陶芸・蒔絵など光悦の芸術精神を今に伝える場所として、多くの人々に親しまれています。
利休居士三百五十年遠忌
―りきゅうこじさんびゃくごじゅうねんえんき―
昭和15年(1940年)、千利休の没後350年を記念して三千家が合同で開催した大規模な追善法要および茶会。近代茶道復興の象徴的な出来事とされる。
大徳寺
―だいとくじ―
京都市北区紫野に位置する臨済宗大徳寺派の大本山。1315年に大燈国師『宗峰妙超』によって創建。 応仁の乱で一度荒廃しましたが、『一休宗純』によって再興。 境内には20以上の塔頭寺院があり、龍源院、高桐院、大仙院、黄梅院、瑞峯院などが一般公開されています。 特に、三門「金毛閣」は千利休が二階部分を増築したことで知られてる。
献茶式
―けんちゃしき―
神仏に抹茶を点てて奉納し、感謝や祈願の心を捧げる茶道の儀式です。起源は古く、茶の湯の精神と信仰が融合した厳粛な行事として、寺社などで執り行われます。三千家の家元が奉仕することも多く、点前や道具、装束なども格式を重んじたものが用いられます。献茶の後には一般参列者向けの呈茶席が設けられることもあり、茶道の神聖性と文化的意義を広く伝える場となっています。
北野大茶湯
―きたのおおちゃのゆ―
天正十五年(1587年)、京都・北野天満宮で豊臣秀吉が催した大規模な茶会。身分や階級を問わず多くの人々に茶が振る舞われたことで知られ、茶の湯の民衆化を象徴する。
昭和北野大茶湯
―しょうわきたのだいちゃのゆ―
昭和十一年(1936年)、豊臣秀吉の「北野大茶湯」350年を記念して開催された大茶会。京都市内各所で百を超える茶席が設けられた。
北野天満宮
―きたのてんまんぐう―京都市上京区にある神社で、947年に創建。 学問の神様として知られる『菅原道真』を御祭神とし、全国約1万2000社の天満宮・天神社の総本社。 境内には約1,500本の梅が植えられ、2月下旬から3月中旬にかけて見頃を迎えます。 また、毎月25日には「天神市」と呼ばれる縁日が開催され、多くの参拝者で賑わいます。