

1-3|利休の師|01.利休の出自|千宗易利休|抛筌斎
利休に師はいたのか? もしそうなら、誰が彼の「茶」と「こころ」を育てたのか?
堺の豪商・武野紹鷗から「侘び」を学び、大徳寺の禅僧たちから精神的な軸を得た利休。複数の師の存在が、利休の思想を深め、多層的な茶の湯を形づくっていきます。
その師弟関係の中に、利休という存在の核が見えてきます。


1-4|利休の門下|01.利休の出自|千宗易利休|抛筌斎
利休の門弟は、天下人から町衆まで幅広かった——。
武野紹鷗に学び、大徳寺で禅を修めた利休は、自らの「茶と精神」を豊臣秀吉や蒲生氏郷、古田織部など、あらゆる層に伝え広めていきました。
利休という“個人”から始まった茶の湯の哲学が、いかにして“流派”や“文化”として広がったのか。その源流をたどります。


10-1|利休の師|10.利休ゆかりの人々|千宗易利休|抛筌斎
千利休が大成した茶の湯の背景には、三人の師から受けた深い影響がありました。北向道陳からは書院茶の礼法を、武野紹鷗からは侘び茶の美意識を、古渓宗陳からは禅の精神を学び、それらを独自に融合・発展させたのが利休のわび茶です。三人の師の存在は、利休を語るうえで欠かせない重要な要素といえるでしょう。


10-2|天下三宗匠|10.利休ゆかりの人々|千宗易利休|抛筌斎
「天下三宗匠」とは、千利休・今井宗久・津田宗及の三人を指し、信長や秀吉のもとで茶の湯を支えた重要人物たちです。それぞれが異なる茶風をもちながら、時代と共に茶道を発展させ、特に北野大茶湯などの公的茶会では中心的な役割を果たしました。利休と並び称される理由を探ります。


10-3|利休三門衆|10.利休ゆかりの人々|千宗易利休|抛筌斎
千利休の門弟の中でも特に信頼を寄せられた三人の武将、蒲生氏郷・細川忠興(三斎)・芝山宗綱。彼らは「利休三門衆」と呼ばれ、戦国の世にあって利休の茶の湯を学び、武家文化の中にその精神を浸透させました。茶の湯が政治と文化の両面に影響を与えたその背景には、彼らのような存在があったのです。


10-4|利休七哲|10.利休ゆかりの人々|千宗易利休|抛筌斎
利休七哲とは、千利休に深く師事した七人の大名・武将を指す後世の呼称で、茶書『茶道四祖伝書』や『江岑夏書』に基づき伝えられています。彼らは武将でありながら茶の湯を深く学び、利休の精神を実践。武家社会に茶道を広める契機となりました。利休没後もその教えを継ぎ、後世の茶の湯文化に大きな影響を残しました。
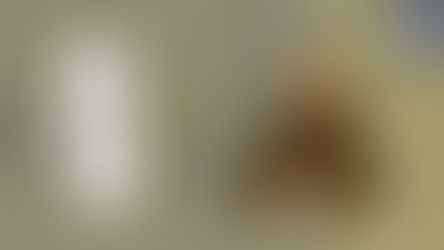

10-5|利休十哲|10.利休ゆかりの人々|千宗易利休|抛筌斎
「利休十哲」とは、千利休に師事した十人の武将・茶人を指す後世の呼称で、「利休七哲」に加えて織田有楽斎、千道安、荒木村重の三名を含みます。彼らは、戦乱の世にありながら利休の茶の精神に深く傾倒し、それぞれの地位や人生を通じてその教えを実践し伝えました。