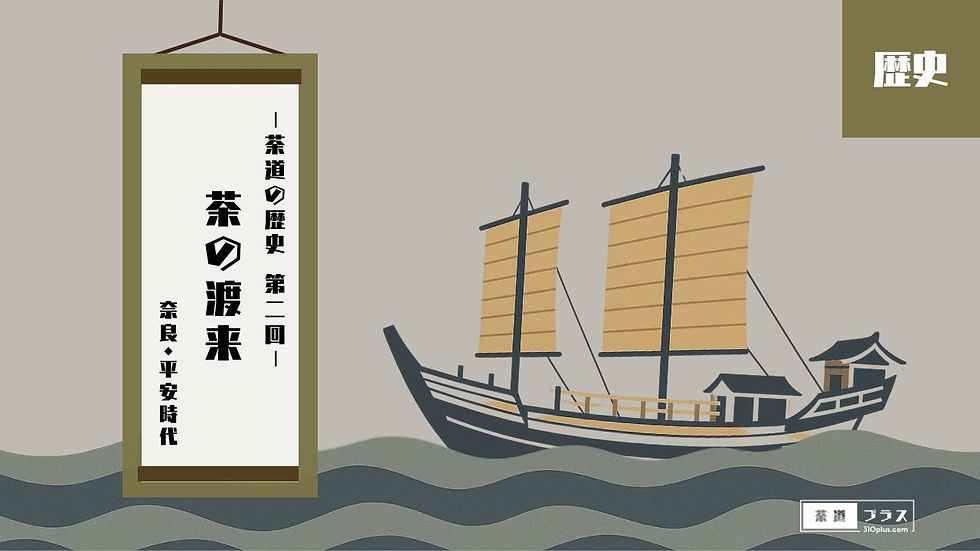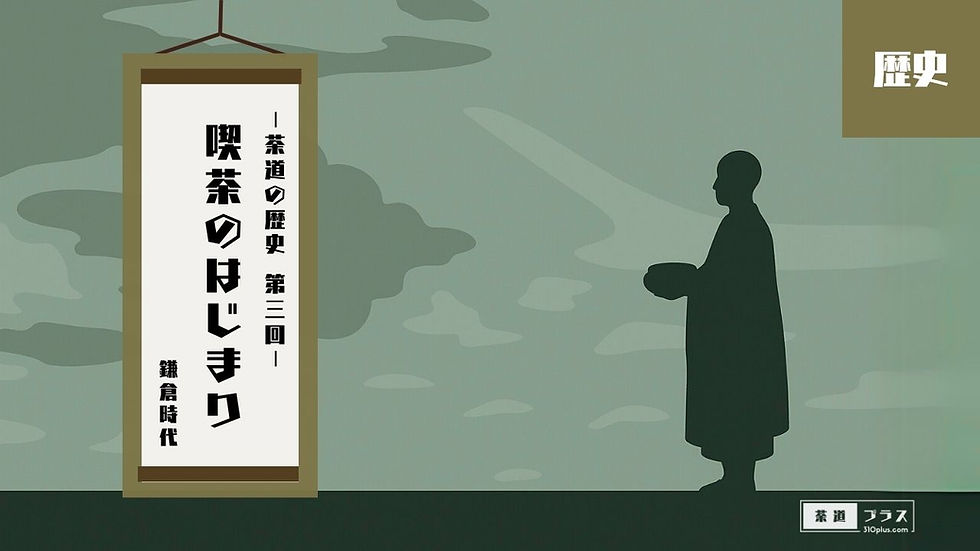2-5|茶の衰退 ~遣唐使の廃止と忘れられた文化~|第2回 茶の渡来|奈良時代~平安時代|茶道の歴史
- ewatanabe1952

- 2025年6月15日
- 読了時間: 4分
全10回 茶道の歴史

■ 第2回 茶の渡来 [5/5] ■
奈良時代 (710年―794年) ~ 平安時代 (794年―1185年)
❚ 忘れられた一碗
かつて、嵯峨天皇**に献上された一碗の“茶”は、文化の象徴でした。
しかし時が流れ、やがてその香りは、宮廷**から消え、記録からも消えていきます。
今回は、日本に伝来した“茶”が、平安時代の中期においてなぜ衰退していったのか――その背景をひもときます。
❚ 遣唐使廃止と文化の断絶

奈良時代(710年―794年)から平安時代(794年―1185年)初期にかけて、日本には中国・唐**の先進文化が数多く伝わりました。
“茶”もまたその一つであり、最澄*や空海*などの留学僧、あるいは遣唐使**によって持ち込まれたものでした。
しかし、寛平六年(894年)、朝廷**は遣唐使の派遣を中止します。
この出来事は、単なる外交上の変化ではなく、日本が唐の文化的影響から距離を取り、独自の国風文化を築きはじめるための第一歩となるものでした。
❚ 茶の衰退と儀式化
遣唐使の廃止に伴い、中国からもたらされた“茶”もまた、次第に人々の関心から遠のいていきます。
十世紀以降、“茶”は主に『季御読経**』など、宮中行事**の中で儀礼的に限られ、日常の喫茶習慣のとしての記録はほとんど見られなくなります。
当時の“茶”は、庶民が日常的に味わうような存在ではなく、あくまで薬効を期待した飲料であり、貴族や僧侶など高貴な身分の人々に限られたものでした。
❚ 国風文化の台頭と喫茶文化の忘却

平安時代(794年―1185年)中期以降、日本は漢詩や仏典を中心とした中国文化から距離を置き、『源氏物語**』に代表されるようなひらがな文学と和風美意識の世界へと進みます。
この国風文化の流れの中で、仏教的儀礼とともに伝えられた“茶”もまた、次第に―“過去の文化”―として記憶の彼方に追いやられていきます。
こうして、九世紀末から十一世紀にかけての日本では、一時的に―“茶の記録”―や―“喫茶の実態”―がほとんど見られなくなる、“沈黙の時代”が訪れることとなるります。
❚ 次なる芽吹きへ

茶の記録が途絶えた時代——―。
今日、その歴史を振り返れば、それは“文化の衰退”ではなく、“再生の準備期間”ともいえるでしょう。
文化とは、常に光の中にあるものではありません。
静けさのなかで受け継がれ、目に見えぬ根を張り、やがて時を待つものでもあります。
この―“沈黙の時代”―があったからこそ、鎌倉時代(1185年―1333年)に訪れる喫茶文化の再興は、より強く、美しく、日本人の精神に深く根づいていくこととなります。
次回は臨済宗**の開祖である栄西**らによって再び“茶”息を吹き返し、やがて、“道”として確立されていく歴史を紐解いていきます。
登場人物
嵯峨天皇
786年―842年|第五十二代天皇|第五十代桓武天皇の第五皇子|
最澄
766年―822年|伝教大師|僧|遣唐使|天台宗開祖|比叡山「延暦寺」開山|
空海
774年―835年|弘法大師|僧|遣唐使|真言宗開祖|高野山「金剛峯寺」開山|
栄西
1141年―1215年|明庵栄西|僧|臨済宗開祖|「建仁寺」開山|
用語解説
嵯峨天皇
―さがてんのう― 786年―842年。平安時代初期の第52代天皇。文化・文芸を奨励し、「弘仁文化」を築いた人物。近江行幸の折に茶を賜り、茶の栽培を諸国に命じたことで、茶文化発展の礎を築いた。
宮廷
―きゅうてい―
唐
―とう―
最澄
―さいちょう―
空海
―くうかい―
遣唐使
―けんとうし― 7世紀から9世紀にかけて日本が中国・唐へ派遣した公式使節団で、律令制度・仏教・漢字文化・建築・服飾など、先進的な文化や制度を学ぶために送られました。特に聖武天皇や最澄・空海らが関わった遣唐使は、日本の政治・宗教・芸術に大きな影響を与えました。894年、菅原道真の進言により廃止されましたが、その遺産は後の日本文化の基盤を形作る重要な役割を果たしました。
朝廷
―ちょうてい―
季御読経
―きのみどきょう― 「季御読経」は、天平元年(729年)にはじまったとされ平安時代(794年-1185年)の終り頃まで続いた「宮中行事」のひとつ。東大寺や興福寺などの諸寺から60~100の禅僧を朝廷に招き3日~4日にわたって『大般若経』を読経し国家と天皇の安泰を祈る行事であり、その中の第二日目に衆僧に「引茶」をふるまう儀式が行われていました。のちに『[宮中行事]季御読経』は春秋の二季に取り行われることとなったが、「引茶」は春のみに行われていたとされています。また「茶」を喫する事も修行の一つであるという意から「行茶」とも呼ばれていました。
宮中行事
―きゅうちゅうぎょうじ―
源氏物語
―げんじものがたり―
臨済宗
―りんざいしゅう―
栄西
―えいさい―